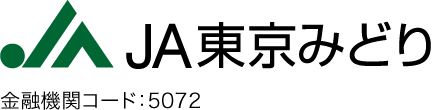2019 新春号 Vol.106
税務・法律・人事・労務管理相談
相続法の大改正に伴う相続実務への影響
1.概要
2018年7月6日、参議院本会議で「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が可決・成立し、7月13日公布されました。民法の債権法大改正に続き、相続法も改正されることとなったのです。この改正は高齢化社会の進展、家族関係の多様化に対応するもので、実務や社会生活に大きな影響を及ぼす改正です。原則として公布の日から1年以内に政令で指定する期日に施行されます。具体的には2019年7月1日に施行されます(但し特例による例外あり)。
2.改正骨子
改正内容は多岐にわたりますが、中でも特に相続実務の際に問題となりうる配偶者居住権制度の新設と遺留分制度の見直しについて解説します。
3.配偶者居住権制度の新設
- (1)制度概要
-
配偶者が亡くなった際、生存配偶者は多くの場合高齢で、長年住み慣れた家に最期まで住み続けたいという希望が強いのが通例です。しかし、旧法下では、被相続人が遺言を残さず死亡した場合、生存配偶者の居住は、事実上のものにとどまり、分割協議においても十分な配慮がなされないのが実情です。
そこで新法は配偶者の居住権を権利として保障しました。すなわち、配偶者である相続人が、①被相続人の財産に属した建物に(単独所有でも共有でも)、②相続開始時に、③無償で、④居住していた場合、相続人は相続開始時に居住していた建物の全部について無償で使用・収益できるようになります(新法1028条1項)。上記要件を満たせば、生存配偶者は「終の棲家」として住み続けることができるのです。これは、たとえ遺産分割、遺贈、共同相続人間の合意がなくとも、配偶者自身が請求すれば、家裁の審判で認められる権利です。原則として終身ですが、遺産分割協議や遺言、家裁審判で期間の定めを設けることも可能です。第三者に対抗するためには登記が必要となります。ただし、遺産分割が終了するまでの間だけ、仮に住まわせて欲しいという場合には登記は不要です。これを配偶者短期居住権といいます(新法1037条)。 - (2)留意点
- 相続税は、「相続又は遺贈により取得した財産」に課税されるので(相続税法2条1項)、配偶者居住権が財産的価値をもつ以上、相続分として扱われるため、相続財産として課税されることになります。税務申告の際にどのように評価計算するかは、今後の基本通達の中で示されることになっているため、留意が必要です。ただし、短期居住権の場合は、その実質は明渡しの猶予に過ぎないため、評価の対象にはならないと考えられています(今後の通達で明記される予定)。なお、配偶者居住権に関する改正部分については2020年7月までに、施行されます。
4.遺留分制度の見直し
- (1)制度概要
-
従来、遺留分減殺請求の行使は物権的な効果(物を直接支配する効果)を生ずるとされてきました。そうすると、対象が不動産の場合、ひとたび遺留分請求権が行使されると、金額で調整する協議が調わない限り、強制的に共有物とならざるを得ませんでした。かかる帰結は、円滑な事業承継を困難にするとともに、共有関係の解消をめぐり新たな紛争を生じさせるものでした。
そこで、新法は、この点を抜本的に改め、遺留分「侵害」請求の効果は、完全に債権的なものにとどまるとしました(支配権ではなく純粋な請求権)。具体的には、遺留分を侵害された遺留分権者は、侵害者である受遺者・受贈者に対し、侵害された遺留分額に相当する金銭の支払いしか請求できないことになったのです(新法1046条1項)。 - (2)留意点
- これによって、被相続人の所有に属していた不動産や株を特定の相続人に集中させることが可能となります。主体が中小企業の場合、既存の経営承継円滑化法を活用することも考えられますが、遺留分制度と要件・効果が異なることから、どちらの制度を活用した方がメリットがあるかを具体的状況に応じて慎重に判断する必要があります。
5.その他
上記以外にも、遺産分割や遺言制度に関する見直し、相続人以外の者の貢献を考慮するための制度新設などが行われました。詳細なご質問等は税理士法人青山&パートナーズにお問い合わせください。